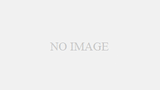「なかなか妊娠できない」「タイミングを合わせても成果が出ない」——そう感じたとき、多くの方が不妊治療を検討し始めます。しかし、実際に治療を受けるとなると「どこから始めれば?」「費用は?」「保険は使えるの?」といった疑問が次々と湧いてくるものです。この記事では、不妊治療の基本的な種類と流れ、そして費用や保険制度について、初めての方にもわかりやすく解説します。
不妊治療の基本的な流れ
不妊治療は大きく3段階に分かれ、症状や検査結果によってステップアップしていきます。
1. タイミング法
排卵日を特定し、性交のタイミングを合わせる方法。最も自然に近い方法で、妊娠を望むカップルの多くがまずここから始めます。
2. 人工授精(AIH)
排卵に合わせて、洗浄・濃縮された精子を子宮に直接注入する方法。タイミング法で妊娠に至らない場合に用いられます。
3. 体外受精(IVF)・顕微授精(ICSI)
卵子を体外で受精させてから子宮に戻す方法。重度の不妊、年齢要因、精子の問題などに対して行われます。
不妊治療の費用の目安
治療法によって費用は大きく異なります。以下は自費診療時の大まかな目安です(2024年現在の平均)。
- タイミング法:月1万〜3万円程度
- 人工授精:1回あたり1万〜3万円
- 体外受精(IVF):1周期あたり30万〜60万円
- 顕微授精(ICSI):1回あたり40万〜70万円
加えて、採卵、凍結保存、ホルモン注射、薬剤費などの追加費用が発生する場合もあります。
保険適用の対象と条件
2022年4月より、日本では一定条件のもとで不妊治療が保険適用となりました。主なポイントは以下の通りです。
- 対象年齢:治療開始時点で43歳未満
- 適用回数:40歳未満は最大6回、40歳〜42歳は最大3回
- 対象治療:タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精など
- 保険点数:例)採卵5万円前後、胚移植3万円前後(自己負担は3割)
※年齢・疾患・医師の判断によって適用範囲は異なるため、事前に医療機関での確認が必要です。
助成制度と補助金の活用
保険適用の対象外になった場合や保険適用終了後は、自治体によって独自の助成制度が設けられていることもあります。以下の制度を確認しましょう。
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業(旧制度):一部自治体で継続中
- 地方自治体の独自支援金:所得制限や対象年齢あり
- 医療費控除:年間10万円を超える医療費は確定申告で一部戻る可能性あり
不妊治療を始めるときの心構え
治療には時間もお金もかかるため、パートナーとしっかり話し合いながら進めることが大切です。また、妊活中の心のケアも重要です。不妊専門の心理カウンセリングや、同じ悩みを持つ人たちのコミュニティを活用することもおすすめです。
まとめ
不妊治療は、知識がないまま踏み出すにはハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、正しい情報を得て準備を整えれば、自分たちに合った方法が見つかるはずです。費用や保険制度についても、事前に理解しておくことで安心して治療を進めることができます。焦らず、ふたりで歩む妊活の第一歩を踏み出しましょう。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
妊活・妊娠準備の完全ガイド|心と身体を整える第一歩